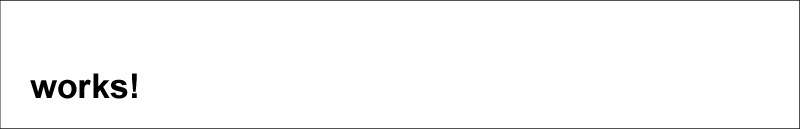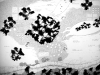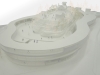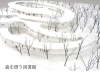- 「集いのオヘソ」/豊田 直樹
全世代が集まり、新しい習慣や関係を持つことができ、日常風景をより豊かになるようにと集いの場を提案します。
敷地を武蔵野市中央公園に設定し、郊外の穏やかな地域の身の丈に合った建築を試みます。
集うところにはオヘソがあるべきだと考えます。
オヘソはそこで営まれる暮らしの重心であり、この重心とバランスをとることで、他の全てのしつらえが決まっていきます。
オヘソを中心とした一室空間はわずかな段差の文節とコアによるスペースの色づけで構成し、これからの変化に柔軟に対応
できる空間にしました。
建物内の暮らしはオヘソでつながり、どこにいても全体を見渡すことができます。
そこに集った人たちの暮らしが滲み出し、建築がだんだんと背景になってこの建築が地域のオヘソとなって、根強く物語や
風景を循環していけたらいいなと思います。
選抜作品
- 「居場所」/小林 研太
雑多な立川の繁華街の中央に住み、暮らして行く。
- 決して良い住居環境とは言えないが、だからこそ住めれば良いような、この土地に住む人間には相応しい。
そこで最低限の住居環境が連なったような長屋のような空間を設計した。
雑多外部空間はスラムのような路地を作り出し、内側に向いた窓は他者の存在を認識させ、
自分が街の一部であると再確認させる。
一階の小規模の飲食店は、繁華街と住居をつなぐ役割をしている。
人々はこの街と関わっていく生活の中で、街の中に様々な居場所を作っていくのである。
- 「花の器」/小林 真由子
近年茨城県水戸市は中心市街地の空洞化が進む一方、市民が街中アートプロジェクトを企画したり、
アートマネージメント団体を発足するなど、新たな街のカラーを作り出すべく展開させている。
本計画ではアーティスト・イン・レジデンスを想定した水戸芸術館別館を計画した。
生活空間の中で植物を育てるように皆でアートを育て、招聘アーティストと市民とをテラスでつなぐ、
クリエイティブプレイスの提案です。
- 「屋根とくらす」/佐藤 智世
ひとつの大きなかたまりを分け合い、6世帯がくらすようになっています。
個々の住宅を囲み、その上に大きな屋根をかける事で世帯間の統一化をはかりました。
それと同時に、個々の住まいに暮しながら全体の大きな空間を感じる事が出来るようになっています。
傾斜している土地なので、各家ごとにレベル差があり、エントランスも別の位置に存在します。
屋根を眺めたり、屋根に住んだり、屋根に上がったり、屋根が少しでも生活の一部に関わるようにしたいと考えました。
- 「ジョギングbuilding」/設楽 幸弘
最近、サラリーマンやOLをはじめジョギングがブームである。
皇居周辺では夕方になると多くのひとがジョギングをしている。
しかしいくつかの問題を抱えている。
それは、交通や防犯、天候に左右されること、そしてコミュニケーション
をとる場所がないという問題である。
そこで、これらの問題を解決するために建築内部でジョギングをする施設を提案する。
- 「neutral」/杉本 塁
小学校に見る光景を、風景に少しだけ近づけました。
予想しないものとの邂逅に魅力を感じる。
いつもの道を逸れてみたら、名前も知らない植物が生き物みたいに揺れていたこととか、
浜辺で拾った綺麗な石が予想以上に軽かったこととか、
雨の日にお寺にいたら軒先から滴る雨粒がスクリーンみたいにみえたこととか。
そういった些細といってもいい予期しないものに出会ったとき、
心奪われている状況は自分自身がニュートラルでフラットになっていると感じる。
それはきっと毎日の生活に繋がることだ。
- 「コロニー」/チェ ソンジュ
原宿のキャットストリートの住宅+商業施設。
地域的に原宿はファッションの中心地なので、ここにファッションデザイナーたちが暮らす住宅と
彼らがデザインした商品を販売しながら、外部の人対象に服作り教室とかを開き、
まわりの人との交流が活発になる空間を提案する。
建物の概観の形はアリのすのコロニーのカタチをモチーフにし、
それを部屋ひとつの基本の形にし、設計をした。
- 「Awareness-形態が意識させるもの」/葉山 えりな
駅前の小さな丘の上の神社に人を呼び込むための商業・文化交流施設。
既存の神社の境内、参道に手を加えることなく、丘を囲うように建て、内側の存在を意識させる。
上の階に上がるにつれ、内側に開けていく空間は、神社だけでなく丘の緑をも意識させてくれる。
- 「森を漂う図書館」/村田 耕太郎
スロープを使った新しい図書館のあり方を提案する。
敷地は世田谷区立羽根木公園。急斜面に生い茂る木々の間を縫うように緩やなスロープを走らせ、街と公園の広場をつなぐ。
スロープには本棚が並び、蛇行しながら膨らみ交わることで閲覧室などの機能をくるみ・ショートカットを行う。
図書館は公園の風景を取り込みながら森を浮遊し、重なり合う本棚は森へと溶け込む。
森を散策するように本を探し、読むことができる。
公園を歩きながら所々に現れる細長い図書館は1つの空間として緩やかにつながる。